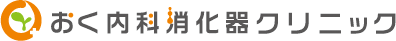メタボリック症候群
内臓脂肪型肥満に複数の生活習慣病が重なった状態の診断・治療
メタボリック症候群とは
メタボリック症候群とは、お腹がポッコリ出た内臓脂肪型肥満の方に、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの複数の生活習慣病が重なった状態のことをいいます。
このような方では動脈硬化が進行し、高率に心筋梗塞や脳卒中が発症することがわかっており、早めの対策が必要となります。現在、日本では成人男性の約2人に1人、女性の約5人に1人がメタボリック症候群かその予備群と推定されています。
⚠️メタボリック症候群の特徴
- 内臓脂肪の蓄積が基盤
- 複数の生活習慣病が重複
- 動脈硬化の進行が促進
- 心血管疾患のリスクが高い
- 生活習慣の改善で予防可能
診断基準
メタボリック症候群の診断には、内臓脂肪の蓄積(腹囲の測定)が必須条件となり、さらに以下の3つの項目のうち2つ以上に該当する場合に診断されます。
📏必須項目(内臓脂肪の蓄積)
腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上
💓高血圧
最大血圧130mmHg以上
または
最小血圧85mmHg以上
🍭高血糖
空腹時血糖
110mg/dl以上
🧪脂質異常症
中性脂肪150mg/dl以上
または
HDLコレステロール40mg/dl未満
各項目について
治療とアドバイス
🍽️食事療法
- カロリー制限
- 減塩(1日6g未満)
- 野菜・食物繊維の摂取
- 規則正しい食事時間
🏃♂️運動療法
- 有酸素運動(週3回以上)
- ウォーキング・水泳など
- 筋力トレーニング
- 日常生活での活動量増加
💊薬物療法
生活習慣の改善だけでは目標値に到達しない場合、各疾患に応じた薬物療法を行います。高血圧、糖尿病、脂質異常症それぞれに対して適切な薬剤を選択し、個々の患者様の状態に合わせた治療を行います。
当院での対応
当院では、メタボリック症候群の診断から治療まで、患者様一人ひとりの状態に応じた包括的な医療を提供しています。
🔍診断・検査
- 腹囲測定
- 血圧測定
- 血液検査(血糖・脂質)
- 心電図検査
💬生活指導
- 食事指導
- 運動指導
- 生活習慣の見直し
- 定期的なフォローアップ